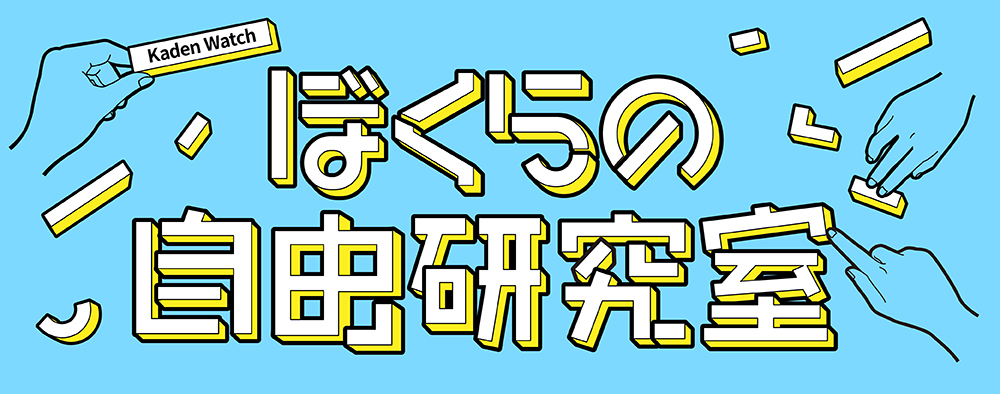2017年12月19日 06:01
先日、JR東海が開催した超電導リニア(以下、リニア)の体験乗車に参加してきた。JR東海では時おり体験乗車の枠を設け、ホームページで募集をしている。ただし、申し込みが非常に多く、プラチナチケットになるので募集のたびに何度もトライするといいだろう。
じつは筆者、10年前の実験車両(MLX01-901)の体験乗車にも当選し(当時の倍率は100倍以上だったと聞く)、今回コレで2回目の乗車となる。
とはいえ、今回の試乗会は、2027年に品川-名古屋間を結ぶ営業車となるL0(エルゼロ)系を使っての運行だ。まだまだ内装を変更したり、細かい改良は残っているものの、ほぼ営業時に近い車両。
以前の実験車両に乗車した10年間でどれだけ乗り心地などが変わったかもレポートしていきたい。
10年前の実験車両と比べると、格段に乗り心地がアップ!
超電導リニアを正しく言うと「超電導磁気浮上式鉄道」となる。読んで字のごとく、磁石の力で浮いて走るのだが、どのぐらい浮くかをご存じだろうか? すでに上海空港と都市を時速430kmで結んでいる上海トランスラピッドは10mmだ。むかし名古屋で開催された「愛・地球博」で有名になったリニモも同じぐらい。
しかし、JR東海が中心になって開発しているリニアは、その10倍以上の100mmも浮いて走る。なぜなら日本のリニアは、営業運転を時速500km行う予定で、地震の多い日本を安全に走行させるためだ。じつに日本の鉄道らしい考え方だ。これまで数々行ってきたテスト走行では、地震も想定したさまざまな試験を実施しているという。
この浮上走行は、電磁誘導という物理現象を利用していて、その現象が起きるのは時速150km程度。それまでは、車両の床についている空回りするゴムタイヤで支えている。レールに相当するものといえば、道路わきにあるU字溝のようなガイドウェイだ。これに沿ってリニアは走る。
駅を出発してから時速150kmになるまでは、新幹線とそれほど変わらない。違うのは、鉄輪ではないため自動車のようなタイヤが地面を叩くロードノイズがする点と、モーターの唸りが聞こえない点だ。
時速150kmを超すとタイヤを車両に引き込み、浮上して走る。飛行機のようにタイヤを引きこむ音が聞こえたかと思うと、ふわっとした軽い浮遊感を覚え、タイヤのロードノイズがなくなりいきなり静かになる。車内の静かさは、まるで新幹線のグリーン車に乗っているような感じ。飛行機の苦手な原因のひとつに、飛んだ瞬間の浮遊感の気持ち悪さがある。10年前のMLX01は、飛行機と同じ気持ち悪さがあり、浮上走行した瞬間に車内が「今のなに!?」とざわついていたが、L0系は浮上した瞬間がほぼわからないレベルまで乗り心地が改善されていた。
ガイドウェイの両脇には磁石(正しくはコイル)がついていて、車両を浮上させると同時にガイドウェイの中心に車両をガイドするレールの役目も担っている。一般的な鉄道では、2本の鉄のレールで車両を案内し支えるが、リニアの場合は磁石が案内し浮上するのだ。
それゆえ時速150km以上の浮上走行になると、どこにも接触することなく走るため、ほぼ無音に近い状態だ。あえて言うなれば、ガイドウェイの中を飛んでいる状態。新幹線はパンタグラフから電気を取るので、その音が聞こえたり、架線を支える電柱を通過するたびに「シュン! シュン!」音が聞こえるときがあるが、リニアにはそれもない。しかも、飛行機のようにシートベルトを締める必要もないのでリラックスできる。体験乗車では立ち歩き禁止だが、営業運転では新幹線と同じようにトイレに立つことも可能だ。
加速感も新幹線以上にいい。新幹線は、鉄の車輪と鉄のレールの摩擦力で走るため、あまり急加速すると車輪が滑ってしまう。なので、急加速や坂道が苦手だ。しかし、リニアは浮いている車両を磁石の力で引っ張るので、新幹線より加速がいい。さらにリニアは、飛行機のように限らせた滑走路の中で急加速しなくても浮上できるため、シートベルトがなくても安心して乗車できる。
新幹線の速度を超える300km以上になると、「ゴー」という風切り音が目立つようになる。また、わずかに低音でうなるモーター音もする。しかし、車内を与圧しているので、耳が少し遠くなり、これまた静かさを助長する。
気になる車窓は、ほとんど見えない。実際の営業線では、風景が見えるところが増えるかもしれないが、都心から神奈川県までは大深度地下を、山梨・長野・岐阜は山間部なのでほぼトンネル。名古屋近辺もまた大深度地下を通る予定なので、車窓は期待しないほうがいいだろう。また、リニアは浮上走行するため、一般的な鉄道に比べて雪や雨といった気象の影響を受けにくい。非接触で走行音はしないが、風切り音や磁力をできるだけ軌道外に漏らさないようにするための配慮から、見通しが利く場所もシェルターが囲われる部分が多くなるだろう。感覚的に言うと、夜の新幹線で静岡や岐阜、滋賀あたりを走行しているような感じだ。
時速500kmの世界は、そんなトンネルの中を走行するので、速度感はあまりない。それ以上に凄いのは、時速500kmという速さなのに、新幹線程度しか揺れないという点。
10年前に乗車したMLX01は500kmで走行すると、ペットボトルの中の飲み物は大きく揺れ、「これは車内販売のコーヒーなんて飲めないな」という印象だったが、L0系はとにかく揺れない。細かい振動こそあるものの、下記の写真のようにペットボトルのお茶は波立たないのだ。
なお、リニアの最高時速は603kmだが、2027年の営業運転では最高速度を500kmとしている。そんな500kmの世界に慣れてしまうと、減速するとノロノロに感じる。音もそれほど聞こえない300km程度では、体感速度100kmほどしかなく、え? まだ新幹線ぐらいの速度? と驚いたほどだ。
20分ほどの体験乗車を終えると、再び駅に到着するが、プシュとエアーの抜ける音がする。これは車内が与圧されているためドアを開けると、車内の空気が外に抜けるためだ。
およそ43kmの実験線を1往復半、L0系に乗車したが、10年前のMLX01に比べると高速走行時の安定性と乗り心地が格段によくなっていた。また、浮上した瞬間の気持ち悪さもほとんどない。
磁力によって電子機器に影響が出ることも、まったくと言っていいほどないようだ。ビデオやスマホ、デジカメに時計はきちんと動作していた。また、人体への磁力の影響を心配される方もいるようだが、加速中に異変を感じたり、下車してから気分が悪くなるようなこともなかった。
10cmも浮上する日本の超電導リニアのしくみ
リニアが「なぜ150kmにならないと浮上しないのか?」という疑問を持つ人も多いはず。飛行機なら翼があるので、ある程度の速度にならないと翼が浮く力を得られないというのは合点がいくが、リニアの場合イマイチわからない。
先ほど電磁誘導という物理現象を利用していると軽く触れた。この現象は、電線をぐるぐる巻きにしたコイルに、磁石を素早く近づけたり、離したりすることで、コイルに電気が流れるというものだ。そして、「コイルに電気が流れると、そのコイルは電磁石になる」というのをむかし習った覚えはないだろうか? つまり、リニアに搭載されている磁石が、軌道に設置されているコイルを走り抜けると、コイルは自然に電磁石となり、車両の磁石と軌道のコイル(磁石)の力によって浮上する。
でも、ゆっくり磁石を近づけたり離すと電気はほとんど流れない。大切なのは「素早く近づけたり離したりしなければならない」点だ。リニアの車両が浮く時速150kmというのは、車両の磁石と軌道のコイルで、自分自身を持ち上げられる最低限の素早さ=速度というわけだ。
速すぎると浮きすぎちゃうんじゃないの? という心配もあるだろう。でも軌道のコイルは8の字になっていて、上部が磁石のS極、下部がN極というようになる。一方で車両の磁石は、超電導磁石のある断面で見ると(下のイラスト参照)、車両左側がN極、右側がS極というようになっているので、車両が浮き上がり過ぎになると、軌道と車両の磁石が引き付け合って浮かないようになる。
今回乗車してわかったのは、ほとんど上下の揺れは感じられなかったこと。もちろん、車両と磁石(台車)のサスペンションの影響もあるかもしれないが、たとえ500kmで走っても新幹線と変わらない揺れ程度だ。
2本のレールに相当する案内も磁石
リニアには、鉄道の象徴である2本のレールがない。でもレールに相当するのも、これまたU字溝のガイドウェイ両サイドに取りつけられたコイルだ。
「さっき横についているのは浮上用と説明したじゃないか!」という声も多いはず。じつは、このコイルは浮上用とレールに相当する案内用を兼用しているのだ。しかもこれまた、先述した電磁誘導の物理法則。
案内用として機能する場合は、コイルに電磁石を素早く近づけると、車両の磁石と軌道の磁石が反発して元に戻ろうとする。その反対側では、車両と軌道の磁石は素早く離れようとすると、互いが引き付けあうようになる。でも、これは浮上時と同じで、ある程度の速度が必要になるのだ。その速度が150kmであり、じつはそれまではミニ四駆のように各車両の横についている車輪を使って、軌道中央に車両をガイドしているのだ。
こうしてリニアは、時速150kmを越えると、磁石の力によって、ガイドウェイの床から10cm浮上し、さらに左右のガイドウェイ中央に位置づけられるようになっている。しかも、コンピューターで磁力を調整する必要はなく、ただ150km以上の速度で走っていれば、自然に浮上し軌道に沿って走る。
不思議な現象なので、なかなかわかりにくいが、これはリニア見学センターでしくみを説明する模型や、おもしろい実験でわかりやすく解説してくれる。もし、リニアに乗ったり見学に行ったりする際には、センターもあわせて立ち寄ってみると理解が深まるだろう。
だいぶ盛り上がってしまったので、後編ではリニアのモーターや超電導磁石についてご紹介しよう。