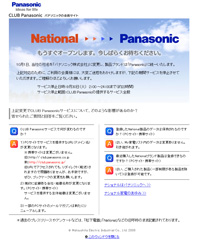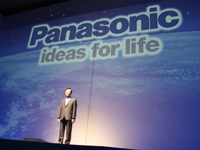|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/03/30 】 |
||
| ||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
| ||
【 2009/03/26 】 |
||
| ||
| ||
【 2009/03/25 】 |
||
| ||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
| ||
【 2009/03/23 】 |
||
| ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大河原克行の「白物家電 業界展望」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
大河原 克行
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、松下電工はパナソニック電工へと社名を変更。あわせて松下グループ各社も、パナソニックを冠した社名へと変更する。 そして、この社名変更を機に、白物家電のブランドである「ナショナル」を、「パナソニック」へと一本化することに着手。2009年度をめどに、流通や商品戦略面における環境が整い次第、統一することになる。
2009年度を最終年度とする中期経営計画GP3では、「グローバルエクセレンスへの挑戦権」の獲得を目指し、連結売上高10兆円、ROE10%以上を数値目標に掲げ、世界ナンバーワンの電機メーカーへの足がかりとする考えだ。社名変更は、このグローバル戦略を見据えた大きな一歩ともいえる。 「今年、松下電器は創業90周年を迎えた。社名変更を100周年まで待てばいいという声もあるだろう。だが、グローバルな競争をするなかで、一刻も早い経営判断が求められており、3カ月、6カ月、1年の遅れが致命傷になる。100周年のときには、世界一の電機メーカーになることを目指すという点では、社名変更はいましかない」 大坪社長は、2006年の社長就任会見時にも、自らの役割として「グローバル化」を掲げていた。 海外フタ桁増販、海外売上高比率60%という指標を具体的に打ち出し、北米、欧州に加え、BRICsとベトナムを重点市場に、富裕層を狙った事業戦略を明確に打ち出した。 就任直後からBRICsおよびベトナムを精力的に訪問した大坪社長は、当時、「これらの市場において、パナソニックというブランドが、まったく知られていないことを肌で感じた」と、語っていたのが印象的だった。 こうした成長市場での展開を含めて、パナソニックがグローバルで戦うには、社名変更は不可欠な判断だったともいえる。 「従来、松下、ナショナル、パナソニックに分散していた力を、社員の一秒の努力、一滴の汗も無駄にせずに、パナソニックに結集したい。これが、もっと高いレベルの企業になるための要素。パナソニックといわれて、日本人が感じるイメージと同じイメージを、世界中の国々で、世界の人たちに、理解してもらうための努力をする必要がある」。 ● ナショナルの名前が消える白物家電事業でのチャンスとは
「ナショナル」のブランドは、1925年、松下幸之助氏が考案し、登録したブランドだ。 新聞を見ていた幸之助氏が、紙面の「インターナショナル」の言葉を見つけ、そこから、インターをとった「ナショナル」という言葉が、「国民の」、「全国の」という意味であることを知り、それを商標として登録した。 ナショナルの商標を利用した第1号商品は、1927年の自転車用/手提げ用兼用の角形電池式ランプの「ナショナルランプ」。1年後には、月3万個を売る大ヒットとなった。 それから81年の長い年月を経過し、日本を代表する家電ブランドとして、多くの人に親しまれた「ナショナル」の文字は消えることになる。 ナショナル商品のマーケティング部門を統括する高見和徳常務役員は、「ナショナルのブランド価値は、十分熟知している。多くのお客様、販売店様に、長年に渡りご愛顧いただき、育てていただいたからこそ、いまがあることも十分承知している」と前置きしながら、「しかし、ナショナルブランドからパナソニックブランドへの変化こそ、我々にとって、大きなチャンスになる。それをご理解いただきたい」と語る。
パナソニックへのブランド変更は、こうした地域販売店や長年のナショナルユーザーにとって、大きなインパクトが明らかだ。 「ナショナルからパナソニックに変わったことで、売っているメーカーが変わったという認識を持つお客様もいるだろう」との声もある。 そして、ブランド変更の理由として、グローバル戦略ばかりが取り上げられることから、海外戦略を優先し、日本の市場を疎かにするのではないかとの誤解も生まれている。 白物家電の事業部門にとっては、こうした誤解を早期に払拭することが課題だといえよう。
ブランドの一本化にあわせて、白物家電事業部門が開始した「Hello! Panasonic」のキャンペーンは、パナソニックブランドの白物家電の登場感を演出するとともに、ナショナルからパナソニックにブランドが変わっても、引き続き、安心感、信頼感を提供し続けることを訴求することが狙いとなる。 「パナソニックの白物家電であれば、圧倒的な超省エネ、圧倒的な超UD(ユニバーサルデザイン)を実現しているというイメージを作り上げたい」と高見本部長は語る。 これが古くからのナショナルユーザーに対するメッセージともいえるのだ。
実は、裏を返せば、ここに、高見常務役員が語る「チャンス」という意味がある。 他社にはないイメージ、ナショナルから一歩進化したイメージを形成するチャンスでもあるからだ。 そして、ナショナルブランドで比較的弱いとされていた20~30代への訴求もパナソニックブランドでの訴求が可能になるという、プラス要素も見逃せない。 パナソニックブランドでの白物家電のイメージがどんな形になるのか。これからの進化が注目される。 ● パナソニック商品群にも変化をもたらす 一方で、外部からは社名変更の変化がないと言われているのが、これまでにパナソニックブランドで展開してきた、黒物家電といわれるデジタル家電機器である。だが、パナソニック商品部門でも、社名変更による変化を、チャンスに変えようとしている。 デデジタル家電商品のマーケティング事業を統括するデジタルAVCマーケティング本部の西口史郎本部長は、「社内には、Change Panasonicを打ち出し、少なくとも3つ以上の新たな提案をしてほしいと言い続けてきた」と語る。 1月10日の社名変更の発表以降、パナソニック商品に関するマーケティング手法や商品企画、仕事のプロセスにも変化を取り入れようとしている。 例えば、デジタル一眼レフカメラに、カラーバリエーションを用意したのも、変化への取り組み成果の1つだといえよう。
デジタルカメラはもとより、薄型テレビやBlu-ray Discレコーダーなどの商品群において、年末商戦ではどんなマーケティング施策を展開するのか、そして、今後発売されるデジタル家電商品にはどんな変化が表れるのかは、やはり注目ポイントだといえよう。 ● 5合目の登山口からどう登っていくか 大坪文雄社長は、社名変更やブランド統一について次のように語る。「何をもって、グローバルエクセレンスというかによって、指標が変わってくるだろう。もし、パナソニックと聞くだけで、安心感をもって消費行動をとっていただけることを、グローバルエクセレンスの条件とするのであれば、日本国内においては、山登りの5合目にいるという言い方ができる。だが、グローバルという観点では、5合目以下というのは明らか」。
つまり、グローバルエクセレンスという高い山に向けて、ようやく本当の山登りが始まるというのが大坪社長の認識なのである。 「我々が登ろうとしている山は、その高さがどんどん高くなっていく。その変化が激しい山の5合目に到達した時点で、ようやくグローバルエクセレンスへの挑戦権を得たといえるだろう。社名、ブランドを、もっと親しみにあるものにしていかなくてはならない。そのためには、自らの手で開発した商品を、市場にお届けし、またサービスとして提供することが必要であり、ナショナル、松下以上のすばらしいイメージをパナソニックに込めていかなくてはならない。社名を変更して、本当に良かったのか、成功と言えるのか。それはこれからの取り組みがどう受け止められるにかかっている。 車では登ることができない、厳しい登山道の入り口に立ったというのが、社名変更をしたいまのポジションだと、大坪社長は捉えている。 ■URL パナソニック株式会社 http://www.panasonic.co.jp/ ■ 関連記事 ・ パナソニック、“ナショナル”ブランドに幕(2008/09/16) ・ パナソニックブランドによる白物家電事業が本格スタート(2008/09/16) ・ パナソニック株式会社への看板付け替え作業完了(2008/09/29) ・ 東京・汐留のパナソニックリビングショールームをリニューアル(2008/09/30) 2008/10/01 00:00 - ページの先頭へ-
|